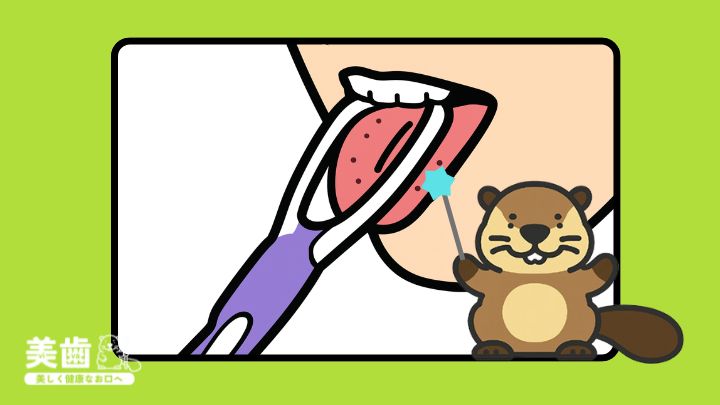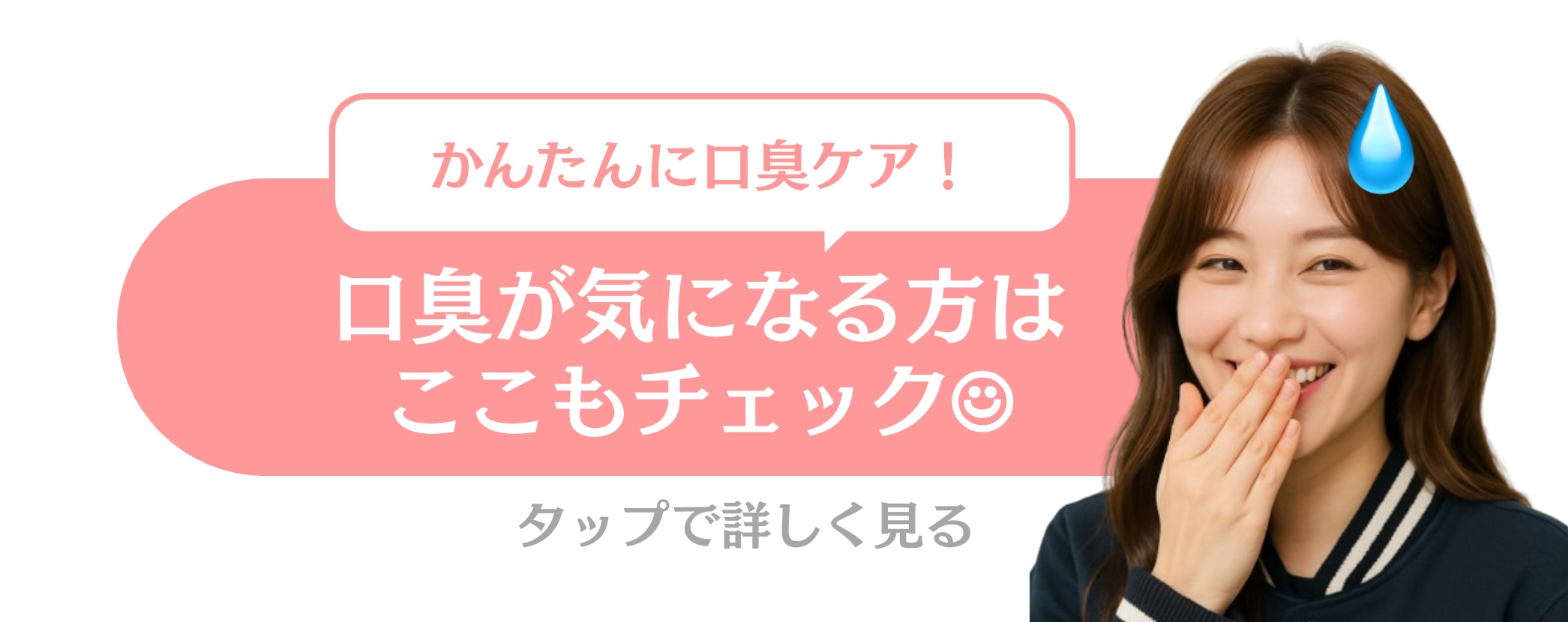※この記事は、PR・広告を含む場合があります。
舌の表面に付着する白い苔状の汚れ「舌苔」は、口臭の主な原因の一つです。口臭の原因の約6割が舌苔によるものと言われています。舌苔は食べかすや剥がれ落ちた細胞などが舌の表面にある舌乳頭の隙間に溜まり、細菌が増殖することで形成されます。この細菌が増殖する際に悪臭を放つ揮発性硫黄化合物が発生し、口臭につながるのです。舌苔はうがいだけでは除去できないため、舌磨きで適切にケアすることが口臭予防に効果的な方法です。
しかし、舌磨きは正しいやり方で行わないと舌を傷つけ、逆効果になる可能性があります。舌は非常にデリケートな組織であり、強く磨きすぎると味を感じる味蕾を傷つけたり、舌の表面を傷つけて炎症を起こしたり、口臭を悪化させたりするデメリットも存在します。
この記事では正しい舌磨きのやり方や頻度、使用するブラシの種類、注意点を解説していきます。記事の内容を参考にしながら、効果的な舌磨きを習得しましょう!
口臭原因の約6割は「舌苔」
舌苔とは、舌の表面に付着する白っぽい苔状の汚れを指します。舌の表面にある「舌乳頭」という細かい突起の隙間に、食べかすや剥がれ落ちた細胞、細菌などが溜まることで形成されます。口臭の原因は様々ですが、その約6割は舌苔によるものだといわれています。(参考:日本歯科医師会)舌苔に含まれる食べかすや細胞は口の中の細菌のエサとなり、細菌が増殖する際に、硫化水素などの悪臭を放つ揮発性硫黄化合物が発生します。健康な舌は淡いピンク色で舌苔もうっすらと薄く付着している状態ですが、厚く付着して黄色く変化している場合は口臭の主な原因となっている可能性があります。
舌苔が溜まる主な原因としては、不適切な歯磨き方法による口腔内のケア不足や、加齢・ストレスなどによる唾液の分泌量の低下が挙げられます。 唾液は口の中の汚れを洗い流す自浄作用や、細菌の増殖を抑える働きがあるため、唾液の分泌量が少ないと舌苔ができやすくなります。 うがいだけでは舌苔を完全に落とすことはできないため、適切な方法でのケアがおすすめです。
舌磨きとは?
舌磨きとは、舌の表面に付着する「舌苔(ぜったい)」と呼ばれる白っぽい汚れを取り除く口腔ケアの一つです。舌苔は、食べかすや細菌、口の中の粘膜細胞の死骸などが混ざり合ってできたもので、特に睡眠中に口の中が乾燥した状態になると蓄積しやすくなります。この舌苔は見た目の問題だけでなく、強い口臭の原因となることもあり、放置すると口腔内の健康を損なうリスクもあります。
通常の歯磨きでは、歯や歯茎の汚れは落とせても、舌の表面にこびりついた舌苔までは除去できません。そのため、清潔な口内環境を維持するためには、歯磨きとあわせて舌磨きを行うことが効果的です。舌磨きを行うことで、口臭の予防はもちろん、味覚が正常に働きやすくなるというメリットもあります。特に舌の中央から奥にかけては汚れが溜まりやすい部位であり、定期的なケアが必要です。
口臭対策を意識している方、マスクをつけたときの口臭が気になる方、人と接する機会が多い接客業や営業職の方などにとって、舌磨きは日々の口腔ケアの中でも重要なステップの一つです。口の中を清潔に保ち、健康と快適な人間関係をサポートするためにも、正しい知識と方法で舌磨きを習慣化していきましょう。
舌磨きの正しいやり方は?
口臭予防や口内環境の改善に役立つ「舌磨き」は、正しいやり方で行うことが大切です。誤った方法で無理に磨くと、舌に傷をつけたり、逆に細菌を奥へ押し込んでしまうこともあります。
ここでは、専用ジェルや舌ブラシを使った正しい舌磨きの手順と、注意点について詳しく解説します。
STEP1|舌を湿らせて乾燥を防ぐ
舌苔(ぜったい)が乾燥していると、舌にこびりついてしまい、きれいに取り除けません。無理にこすれば舌の表面を傷つける原因にもなります。まずは水や専用ジェルを使って舌を十分に湿らせ、汚れを柔らかくしておきましょう。
ポイント:
- 舌苔が乾燥していると、取りづらく傷つきやすくなります。
- 水を口に含むか、専用ジェルをつけることで、舌を磨く準備が整います。
STEP2|舌を前に突き出して汚れを確認
鏡の前で舌を大きく前に出し、どこに汚れが溜まっているか確認しましょう。一般的に舌の中央〜奥にかけて汚れや舌苔が付きやすい傾向があります。
ポイント:
- 舌全体を無理に磨く必要はありません。磨くべき箇所を確認しておきましょう。
STEP3|舌の奥から手前にやさしく磨く
専用の舌ブラシを水で濡らし、湿らせた舌の奥から手前へ向かってやさしく撫でるように磨きます。このとき、力を入れてゴシゴシとこするのは厳禁です。
正しいやり方:
- 舌の奥にブラシをやさしく当て、手前へ向けて3〜4回軽く動かします。
- 汚れをかき出すように動かすのがコツ。
- 往復する動きは避け、舌を傷つけないよう注意しましょう。
STEP4|うがいで汚れをしっかり洗浄する
舌磨きが終わったら、口内に残った汚れをうがいで洗い流しましょう。洗浄には「ブクブクうがい」と「ガラガラうがい」を併用すると効果的です。
▶ブクブクうがいのやり方
- 水を口に含み、頬や唇の内側を膨らませながら3〜4回ブクブクと洗浄。
- 左右、上下と部位を変えて行うのがポイント。
▶ガラガラうがいのやり方
- 水を含んで上を向き、「あー」「うー」と音を立てて15秒ほどガラガラうがい。
- 新しい水で再度行います。
STEP5|ブラシの手入れも忘れずに
使い終わった舌ブラシは流水でしっかり洗い、タオルや清潔なペーパーで水分を拭き取ってから保管してください。湿ったままの放置は雑菌の繁殖を招くため、衛生面において非常に重要です。
舌磨きのまとめ
| ポイント | |
|---|---|
| 準備 | 舌の乾燥を防ぐために水や専用ジェルで湿らせる |
| 磨き方 | 専用ブラシで舌の奥から手前にやさしく動かす |
| うがい | うがいで口内全体の汚れをしっかり洗浄する |
| 後片付け | ブラシは水洗いし、タオルで乾燥させて保管 |
正しいやり方を守れば、舌磨きは毎日の口腔ケアにおいて効果的な習慣になります。必要以上に強く磨くのではなく、やさしく丁寧に行うことで、健康な舌と清潔な口内を保ちましょう。
効果的な舌磨きのコツとは?適切な頻度と注意点
舌に付着する舌苔のケアは、口臭を抑えることに効果的ですが、舌は非常にデリケートなため、適切な頻度と順番、そして注意点を守ることが必要です。間違った方法で行うと、舌を傷つけてしまい、逆効果になる可能性もあります。ここでは、舌磨きの適切な頻度や順番、舌磨きをする上での注意点について解説します。適切なケア方法を理解し、効果的な口臭対策を行いましょう。
舌磨きは1日1回が目安
舌磨きは、口臭ケアに効果的な一方で、やりすぎると舌にダメージを与えてしまう可能性があります。過度な回数で舌を磨くと、舌の表面が傷つき、炎症を起こしたり、口臭を悪化させたりする恐れがあるため注意が必要です。そのため、舌磨きの目安は1日1回にすることが推奨されています。特に、唾液の分泌が減少し、細菌が繁殖しやすい起床後に行うのが理想的です。舌はデリケートな器官であるため、優しく、適切な回数でケアを行いましょう。
舌磨きのタイミングは起床後
舌磨きは朝の歯磨き前に行うのがおすすめです。就寝中は唾液の分泌量が減るため、口の中で細菌が増殖しやすい状態になっています。この状態で飲食をすると、細菌を飲み込んでしまい、胃や腸に悪影響を与えるリスクがあるため、朝の歯磨き前に舌磨きをして口腔内の汚れを取り除くことが大切です。舌磨きで舌の表面に付着した細菌や汚れをきれいな水で洗い流し、口の中を清潔な状態に保ちましょう。
優しく磨く
舌の表面には味を感じる味蕾(みらい)という小さな器官が密集しています。舌を磨く際に強くこすりすぎると、この味蕾が傷つき、味覚障害を引き起こして味を感じにくくなることがありますので注意が必要です。舌を傷つけないよう、舌を磨く際は、力を入れずに優しく磨くことが大切です。
舌ブラシは定期的に交換
舌ブラシは消耗品であり、使用を続けるとブラシ部分が劣化して舌苔を効果的に除去できなくなることがあります。また、使用後のブラシに汚れが付着したまま放置すると衛生的にも良くないため、定期的に新しいものに変えることが大切です。一般的なブラシタイプの舌ブラシは、1ヵ月に1回程度の交換が目安となりますが、商品によっては煮沸消毒が可能で2〜3ヶ月使えるものもあります。一方、ステンレス製の舌ブラシは半永久的に使用できますが、使用後は必ず洗浄し、清潔な状態を保つようにしてください。
舌専用ブラシを使って磨く
口臭予防には舌のケアが不可欠ですが、歯ブラシでは舌を傷つける可能性があります。歯ブラシの毛先は硬いため、デリケートな舌の表面を傷つけたり、味覚を感じる味蕾を損ねたりするリスクがあるため注意が必要です。そのため、舌磨きには舌専用ブラシを使うことがおすすめです。舌専用ブラシは、舌にフィットするように設計されており、歯ブラシよりもソフトな素材でできているため、効率よく優しく舌苔を取り除くメリットがあります。専用ブラシはドラッグストアや薬局で手軽に購入できます。
舌専用ブラシには、主にブラシタイプ、ヘラタイプ、スクレーパータイプ、スプーンタイプがあります。ブラシタイプは歯ブラシに似た形状で、高密度の柔らかい毛先で舌の凹凸に入り込んだ汚れを洗浄するのに優れており、初心者にもおすすめです。ヘラタイプはプラスチックやシリコーン素材が多く、舌への負担が少なく優しくケアできるメリットがあります。ステンレスやチタンなどの金属素材のヘラやスクレーパー、U字型スクレーパータイプは、洗浄力が高いですが、力を入れすぎると舌を傷つける可能性があるため注意が必要です。しかし、衛生的で長く使え、持ち運びや収納に便利なコンパクトなものもあります。舌の先から奥まで、自分の舌に合った素材や形状の専用ブラシを選び、正しくケアをして口臭対策を行いましょう。
舌ブラシの種類は?

舌ブラシには、大きく分けて以下の種類があります。それぞれのタイプで舌の汚れである舌苔へのアプローチが異なるため、特徴を理解した上で自分に合ったクリーナーを選ぶことが大切です。
| タイプ | 特徴 | 使用感・メリット | 素材 | 注意点 | 持ち運び・収納 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラシタイプ | 歯ブラシに近い形状で、細かな毛先が舌の凹凸にフィット | 舌の汚れをしっかり掻き出せて洗浄力が高い。初心者にも使いやすい | ナイロン・シリコンなど(専用素材) | 硬い毛は傷の原因に。やわらかく密なものを選ぶのが必要 | コンパクトで収納・持ち運びもラク | ★★★★☆ |
| ヘラタイプ | フラットなヘラ状で撫でるように使用 | 舌に優しく、ケア時の不快感が少ない。えずきにくい | プラスチック・シリコン | 汚れ除去力はやや劣る。何度か繰り返しが必要 | 軽量でポーチにも入れやすい | ★★★☆☆ |
| ステンレスヘラタイプ | スプーンのような形で舌をなぞる | すっきり感があり、金属製で洗浄しやすく長持ち | ステンレス・チタンなどの金属 | 強く押しすぎると傷になるので力加減に注意 | 細身でケースに収まる。薬局では衛生用品コーナーにあり | ★★★★☆ |
| スクレーパータイプ(U字型) | 舌全体にフィットするU字のカーブ構造 | 広い範囲を一度にケアでき、すっきり感も強い | 金属(ステンレス・チタンなど) | 重さがあり、力加減や保管に注意。えずきやすい場合も | サイズが大きめで収納や持ち運びにやや不便 | ★★★★☆ |
ブラシ型舌クリーナー
歯ブラシに似た形状のブラシ型舌クリーナーは、舌の表面を優しく磨ける点が特徴です。ヘッドに植えられた柔らかい毛が、舌の細かな凹凸に入り込み、舌苔を効果的に取り除けます。普段使い慣れている形のため、初めて舌磨きをする方でも扱いやすい点がメリットです。また、細かい部分までしっかりケアできるため、汚れを落としやすいのも魅力です。しかし、強くこすりすぎると舌の表面を傷つける可能性があるため、適度な力加減を意識しましょう。定期的に交換しながら使用し、専用のクリーナーを舌につけてケアすれば、より効果的な舌ケアができます。
ヘラ型舌クリーナー
ヘラ型の舌クリーナーは、舌の表面に付着した舌苔を優しく除去できる点がおすすめです。柔軟なシリコンなどの素材が多く、舌にフィットしやすいため、ブラシ型と比べて舌を傷つけにくいメリットがあります。そのため、舌を優しくケアしたい方におすすめのクリーナーです。しかし、舌の細かい凹凸に入り込んだ汚れを取り除くのは難しい場合があります。
スクレーパータイプ(U字型)の舌クリーナー
スクレーパータイプ(U字型)は、舌磨き用の専用ブラシの中でも特に効率よく汚れを取り除けるアイテムです。名前の通り、先端がU字型にカーブしており、このカーブ部分を舌に当てて、表面をなでるようにして舌苔(ぜったい)や汚れを除去します。U字の形状が舌の形にフィットしやすく、他のタイプと比べて一度に接触する面積が広いため、効率よく舌全体を磨くことができます。しかし金属製のため、力を入れすぎると舌に傷をつけてしまう恐れがあります。舌の感度が高い方や、えずきやすい方には、カーブの圧迫感が負担になる場合もあるため、自分に合ったタイプかどうか見極めることが大切です。
ステンレスヘラタイプの舌クリーナー
ステンレスヘラタイプの舌ブラシは、その名の通りステンレスやチタンといった金属素材で作られた舌磨き専用の器具です。形状は平らなスプーン状や板状で、舌の表面をやさしく撫でるようにして使います。ヘラ状の先端が舌の表面にしっかり当たり、軽い力で舌苔(ぜったい)をそっと取り除ける設計です。金属素材は耐久性に優れている反面、力を入れすぎると舌を傷つけるリスクがあります。舌の奥を磨くときなどは特に、やさしい力加減で扱うことが必要です。
舌磨きで得られる効果は4つ
舌磨きは、口臭ケア以外にも口腔内の健康維持に多くの効果をもたらします。例えば、舌磨きによって、歯磨きの効果を高めることや、感染症・誤嚥性肺炎の予防、そして味覚を正常に保つことなどが可能です。舌のケアをすることで、健康な口内環境を保ち、身体全体の健康にも良い影響を与えます。日々のケアとして舌磨き習慣化することでどんな効果が得られるのか以下で詳しく紹介していきます。
歯磨きの効果を高めることができる
舌の表面に付着した汚れを舌磨きで取り除くことは、歯磨きの効果をより高めることにつながります。舌苔と呼ばれる舌の汚れには、細菌や食べかすが溜まっているため、歯磨きだけでは落としきれない口臭や虫歯の原因となる汚れが口腔内に残る可能性があります。舌磨きを併用することで、口腔内の細菌数を減らし、歯磨きだけでは難しい口臭や虫歯の予防にも効果が期待できます。
感染症予防になる
唾液には「IgA」という成分が含まれており、体内にウイルスや細菌が侵入しないように防御する重要な働きがあります。口の中が不衛生だとIgAの働きに影響を与え、免疫力が低下して細菌やウイルスに感染しやすくなります。口の中を清潔に保つことは、風邪やインフルエンザなどの感染症予防にもつながるため、日々の歯磨きと併せて舌磨きを行うのがおすすめです。特に舌磨きは、口臭の原因となる舌苔を除去することで、口腔内の細菌数を減らし、免疫力アップにもつながります。
誤嚥性肺炎の予防になる
誤嚥性肺炎は、食べ物や飲み物、唾液などが誤って気管に入り、口腔内の細菌が肺に侵入して炎症を起こす肺炎です。特に高齢者や、脳卒中などで飲み込む力が低下している方は、誤嚥性肺炎を発症するリスクが高まります。口腔内の清潔が保たれていないと細菌が増殖し、誤嚥した際に肺に菌が入り込みやすくなるため、口腔ケアが重要です。舌磨きで舌苔を除去することは、口腔内の細菌数を減らし、誤嚥性肺炎の予防につながります。
味覚を正常に保つことができる
舌の表面には、味を感じるための器官である味蕾(みらい)が多数存在します。舌苔が厚く付着していると、味蕾が覆われてしまい、食べ物の味が感じにくくなることがあります。味覚が鈍くなると、食事がおいしく感じられず、満足感が低下する可能性があります。舌磨きによって舌苔を除去することは、口臭の予防だけではなく、味覚を正常に保ち、食事を美味しく味わうためにも非常に大切です。
舌磨きについてよくある質問
ここでは、舌ブラシの頻度に関してよくある質問について回答していきます。舌磨きに使うジェルとは何か、舌磨きと口臭予防の関係性、そして口臭予防以外の効果についても解説していきますので、ぜひ舌磨きの効果や注意点への理解を深めるのに役立ててみてください。
舌磨きをするとなぜ口臭予防になる?
舌磨きは、口臭の主な原因である舌苔を除去することで、口臭予防に高い効果が期待できる方法です。舌の表面に付着する黄色い舌苔は、食べかすや剥がれた細胞、細菌が混ざり合って形成されており、これが口臭の理由となります。舌磨きで舌苔をケアすることは、口腔内の乾燥を防ぎ、細菌の繁殖を抑えることにつながります。しかし、舌磨きだけでなく、歯磨きやデンタルフロスの使用、さらに水によるこまめな水分補給も重要な口臭ケアの方法です。必要に応じてマウススプレーを使用することも効果的な対策になります。正しい方法で舌磨きを行うことで、効果的に口臭を抑え、清潔な口腔環境を維持できます。
舌みがきジェルって何?
舌みがきジェルは、舌磨きの効果を高めるための補助的なアイテムです。必ずしも使用が必要なわけではありませんが、舌を乾燥から守り、より効果的なケアをするためにはおすすめです。特に、舌苔や口臭が気になる場合は、重曹や殺菌成分が配合されたジェルを選ぶと良いでしょう。また、口腔内の乾燥が気になる方には、保湿成分が配合されたジェルが適しています。ジェルを塗布後、舌ブラシで優しく舌を磨き、その後は水やマウスウォッシュでうがいをすることで、さらに効果的なケアが可能です。毎日のオーラルケアにジェルを取り入れることで、清潔な口内環境を維持できます。
まとめ
舌磨きは、口臭ケアだけでなく、口腔内や全身の健康維持にも繋がる有効な方法です。ただし、間違った方法で舌磨きを行うと、舌を傷つけたり、口臭の悪化や味覚障害を引き起こしたりする恐れがあるため注意が必要です。口の中の洗浄不足や唾液の分泌量の低下が舌苔の主な原因ですが、病気が関わっている可能性もあります。舌苔をケアしても口臭がなくならない、舌苔が異常に増えたなど気になる症状がある場合は、専門医に相談して健康状態を確認することも重要です。適切な方法で舌のケアを行い、口臭を抑えながら口腔環境を良好に保ちましょう。